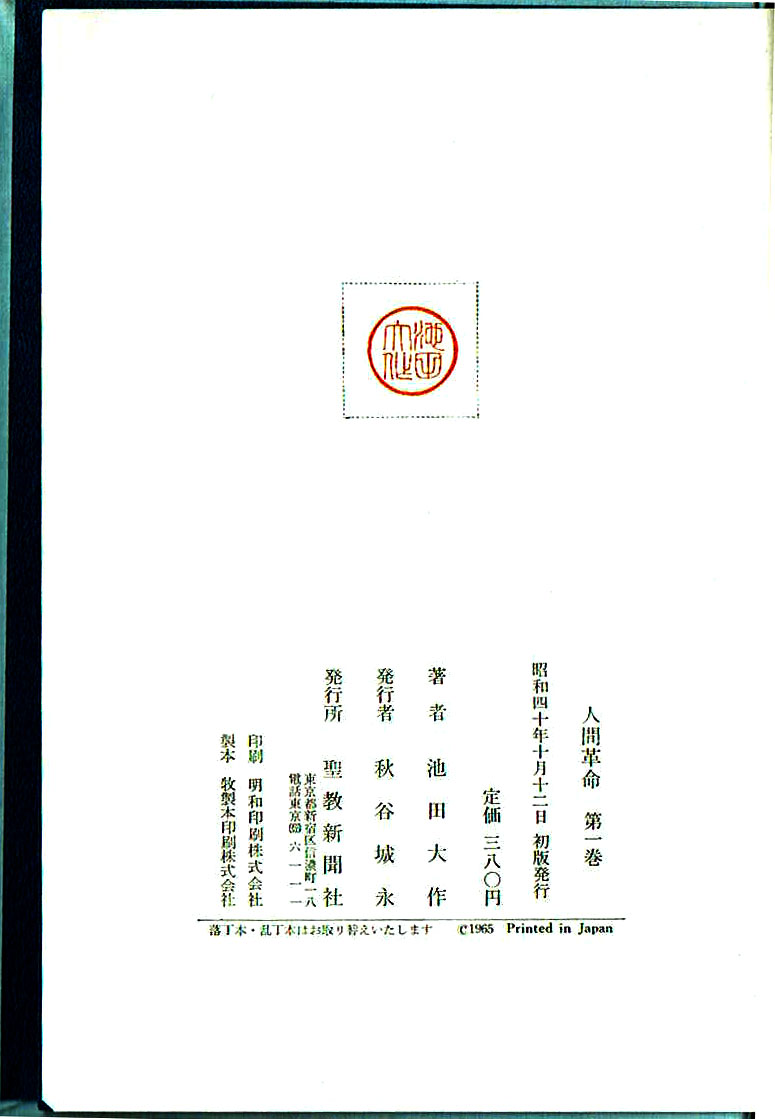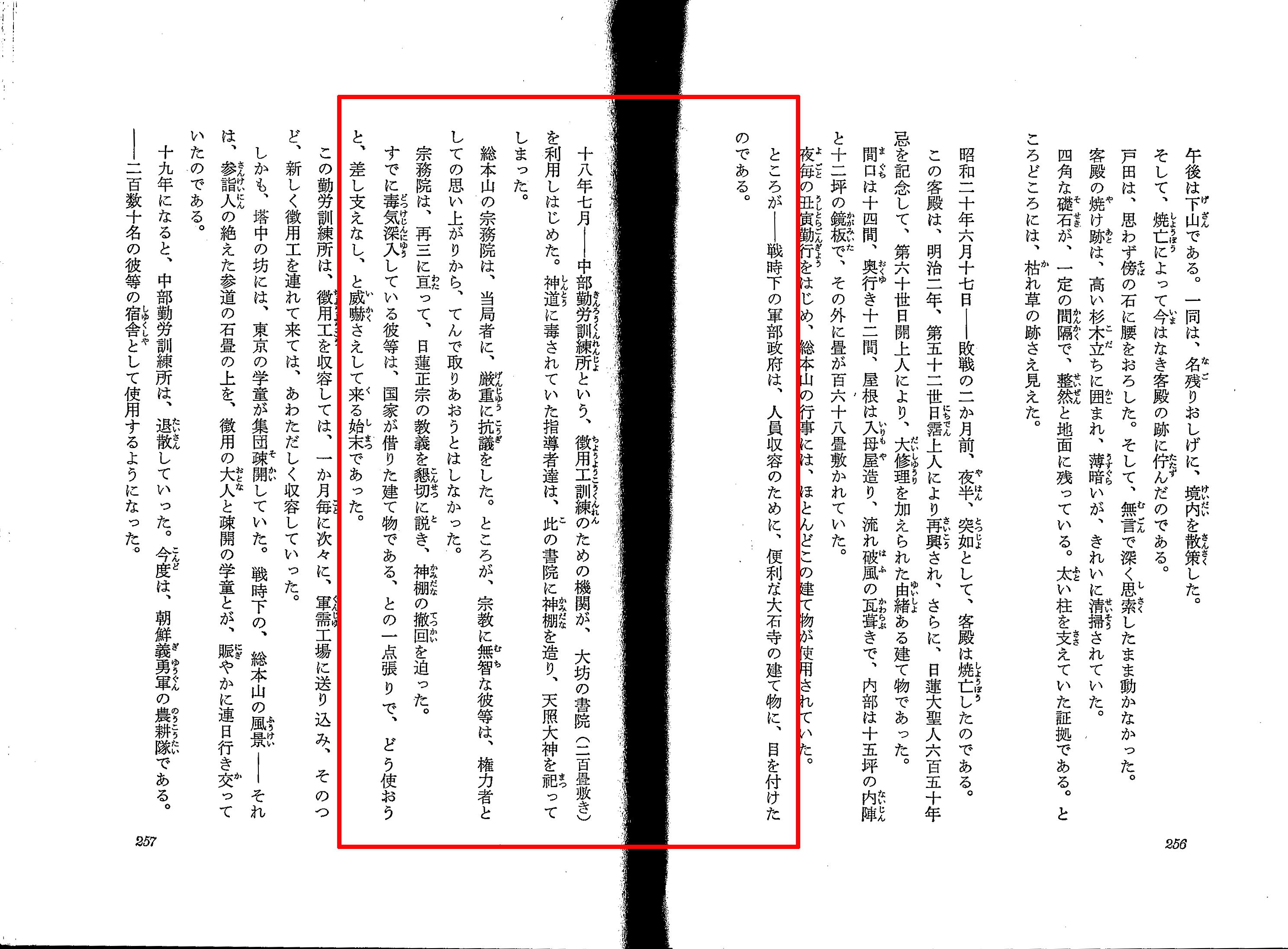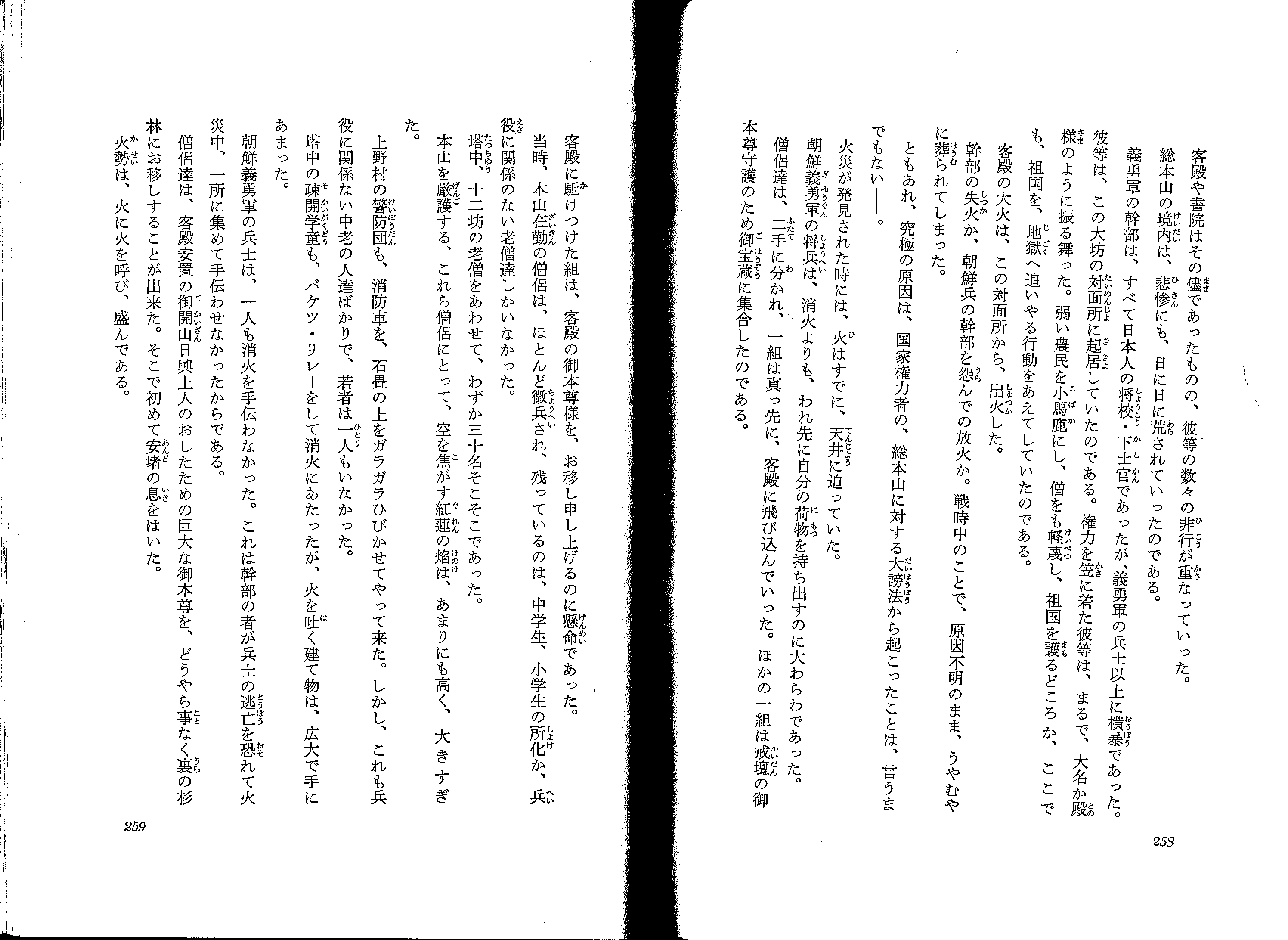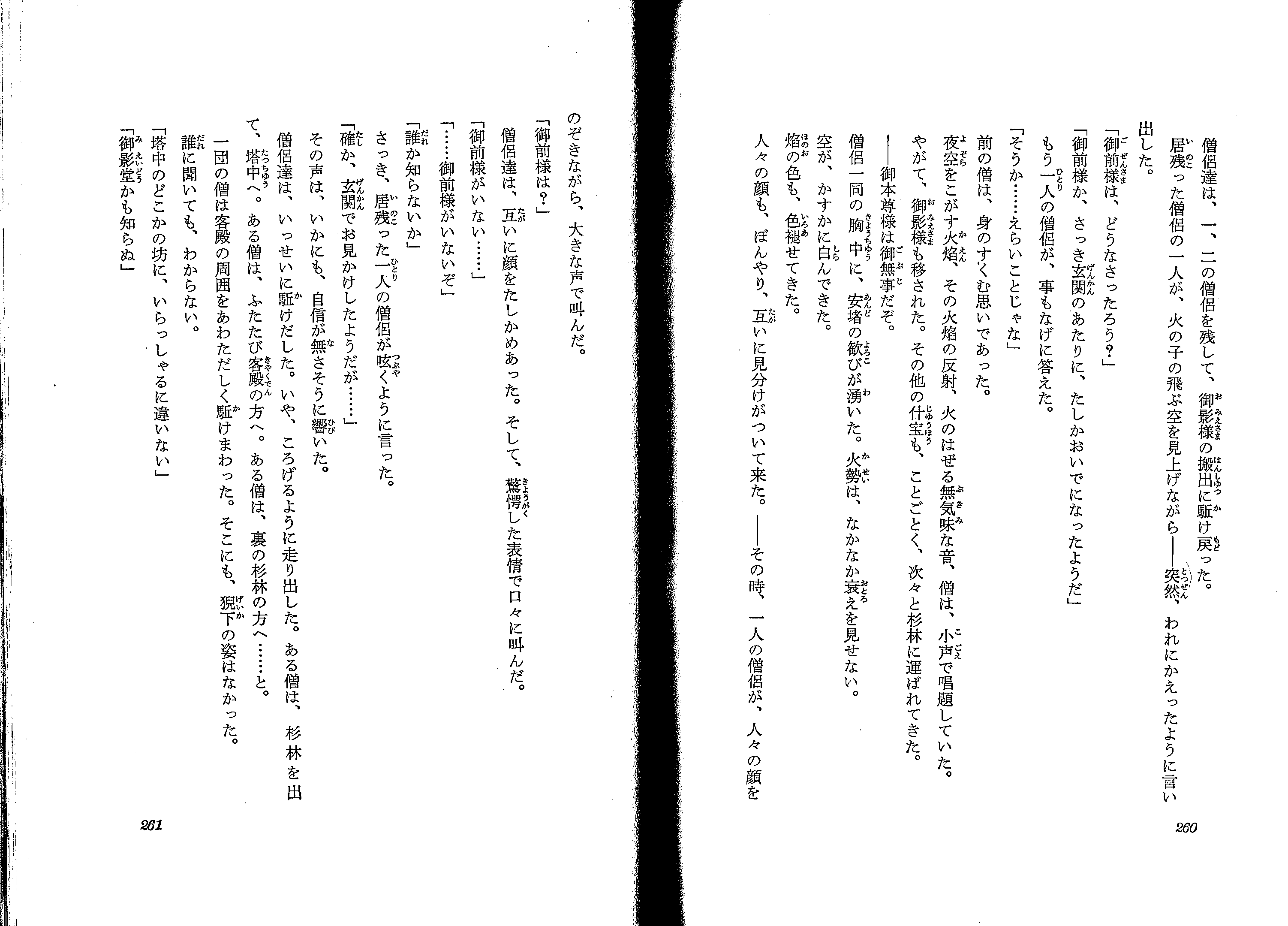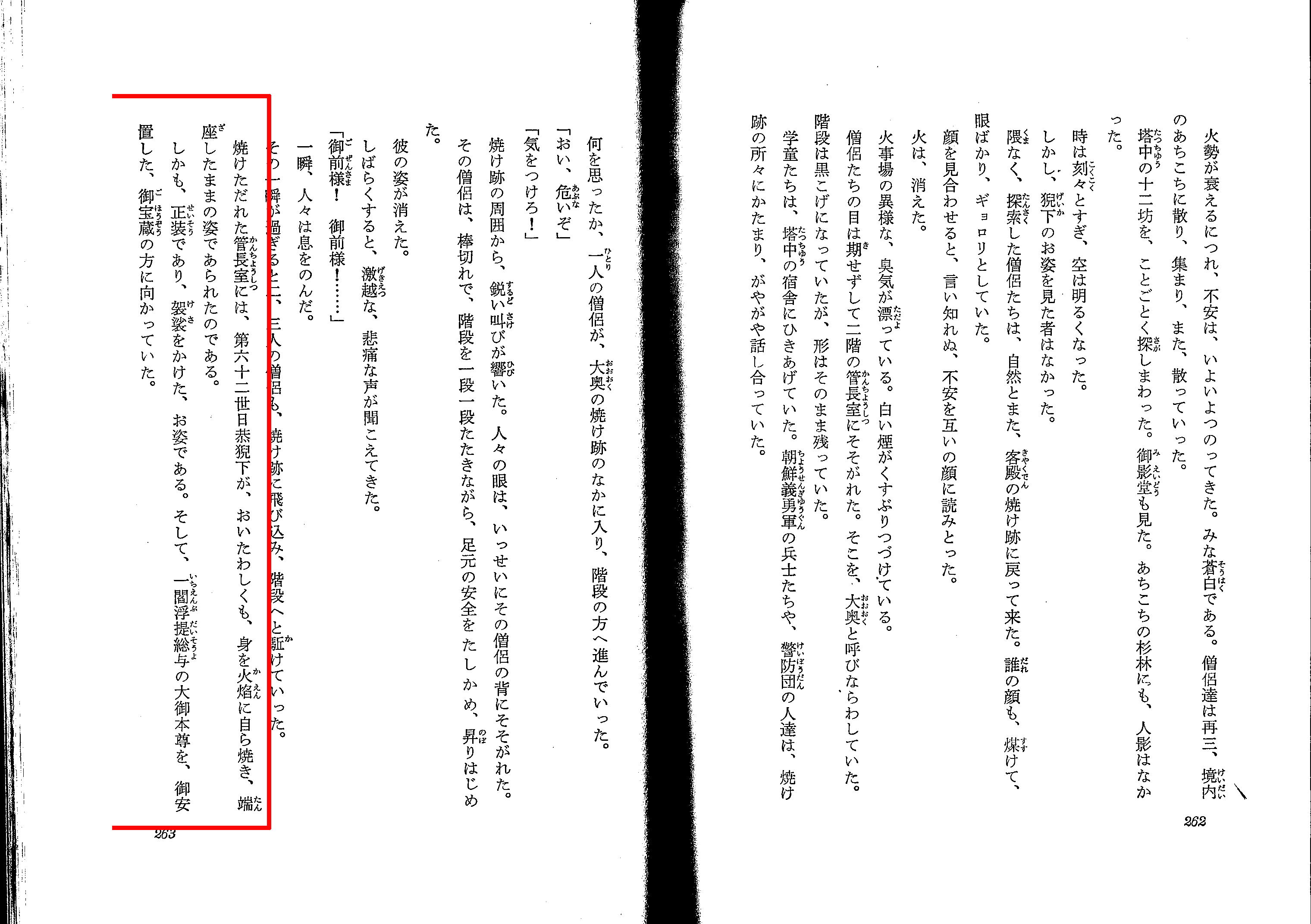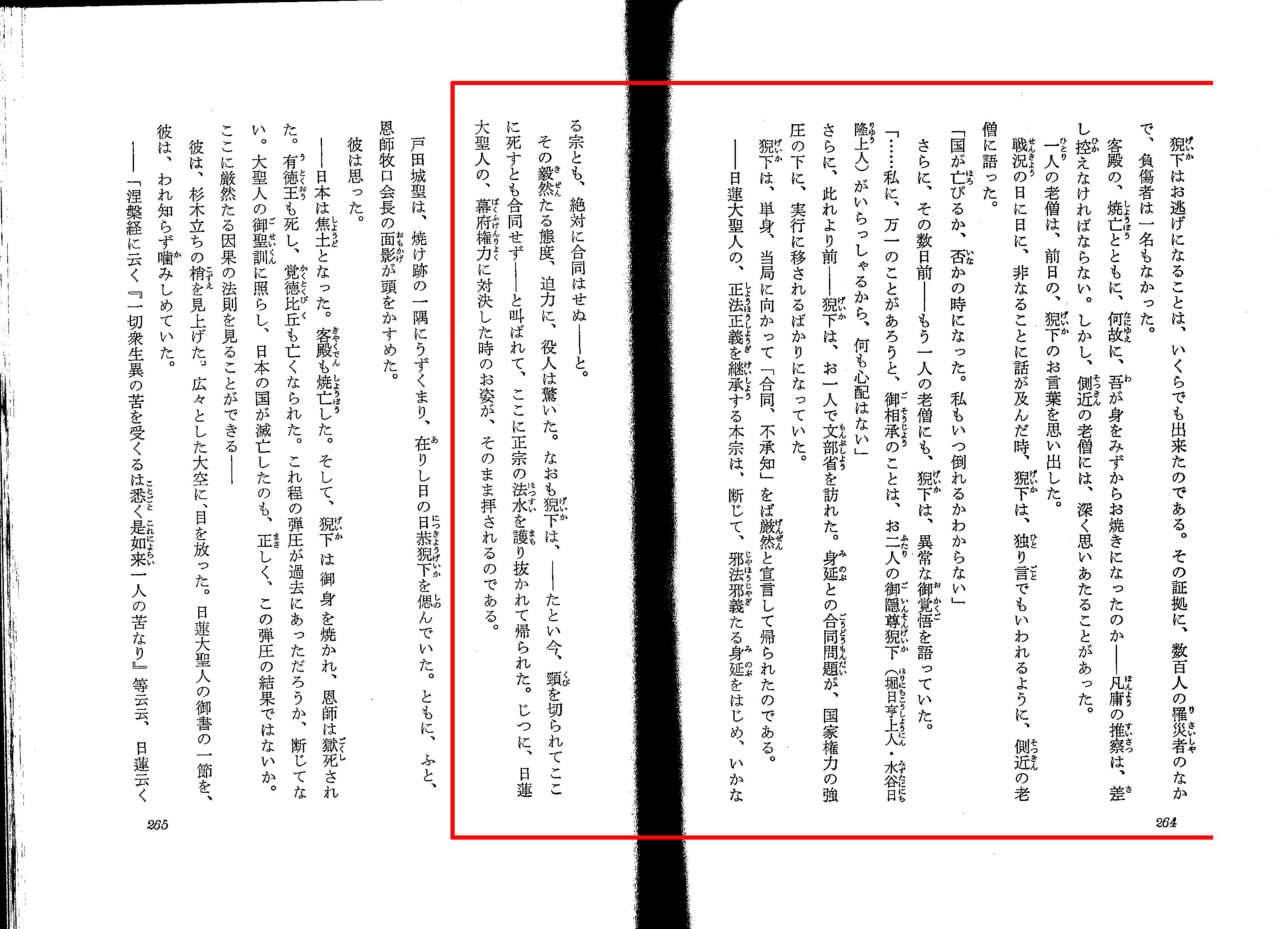昭和二十年六月十七日―敗戦の二か月前、夜半、突如として、客殿は焼亡したのである。
この客殿は、明治二年、第五十二世日霑上人により再興され、さらに、日蓮大聖人六百五十年忌を記念して、第六十世日開上人により、大修理を加えられた由緒ある建て物であった。
(中略)
夜毎の丑寅勤行をはじめ、総本山の行事には、ほとんどこの建て物が使用されていた。
ところが―戦時下の軍部政府は、人員収容のために、便利な大石寺の建て物に、目を付けたのである。
十八年七月―中部勤労訓練所という、徴用工訓練のための機関が、大坊の書院(二百畳敷き)を利用しはじめた。神道に毒されていた指導者達は、此の書院に神棚を造り、天照大神を祀ってしまった。
総本山の宗務院は、当局者に、厳重に抗議をした。ところが、宗教に無智な彼等は、権力者としての思い上がりから、てんで取りあおうとはしなかった。
宗務院は、再三に亘って、日蓮正宗の教義を懇切に説き、神棚の撤回を迫った。
すでに毒気深入している彼等は、国家が借りた建て物である、との一点張りで、どう使おうと、差し支えなし、と威嚇さえして来る始末であった。
この勤労訓練所は、徴用工を収容しては、一か月毎に次々に、軍需工場に送り込み、そのつど、新しく徴用工を連れて来ては、あわただしく収容していった。
しかも、塔中の坊には、東京の学童が集団疎開していた。戦時下の、総本山の風景―それは、参詣人の絶えた参道の石畳の上を、徴用の大人と疎開の学童とが、賑やかに連日行き交っていたのである。
十九年になると、中部勤労訓練所ほ、退散していった。今度は、朝鮮義勇軍の農耕隊である。
――二百数十名の彼等の宿舎として使用するようになった。
客殿や書院はその儘であったものの、彼等の数々の非行が重なっていった。
総本山の境内は、悲惨にも、日に日に荒されていったのである。
義勇軍の幹部は、すべて日本人の将校・下士官であったが、義勇軍の兵士以上に横暴であった。
彼等は、この大坊の対面所に起居していたのである。権力を笠に着た彼等は、まるで、大名か殿様のように振る舞った。弱い農民を小馬鹿にし、僧をも軽蔑し、祖国を護るどころか、ここでも、祖国を、地獄へ追いやる行動をあえてしていたのである。
客殿の大火は、この対面所から、出火した。
幹部の失火か、朝鮮兵の幹部を怨んでの放火か。戦時中のことで、原因不明のまま、うやむやに葬られてしまった。
ともあれ、究極の原因は、国家権力者の、総本山に対する大謗法から起こったことは、言うまでもない――。
火災が発見された時には、火はすでに、天井に迫っていた。
朝鮮義勇軍の将兵は、消火よりも、われ先に自分の荷物を持ち出すのに大わらわであった。
僧侶達は、二手に分かれ、一組は真っ先に、客殿に飛び込んでいった。ほかの一組は戒壇の御本尊守護のため御宝蔵に集合したのである。
客殿に駈けつけた組は、客殿の御本尊様を、お移し申し上げるのに懸命であった。
当時、本山在勤の僧侶は、ほとんど徴兵され、残っているのは、中学生、小学生の所化か、兵役に関係のない老僧達しかいなかった。
塔中、十二坊の老僧をあわせて、わずか三十名そこそこであった。
本山を厳護する、これら僧侶にとって、空を焦がす紅蓮の焔は、あまりにも高く、大きすぎた。
上野村の警防団も、消防車を、石畳の上をガラガラひびかせてやって来た。しかし、これも兵役に関係ない中老の人達ばかりで、若者は一人もいなかった。
塔中の疎開学童も、バケツ・リレーをして消火にあたったが、火を吐く建て物は、広大で手にあまった。
朝鮮義勇軍の兵士は、一人も消火を手伝わなかった。これは幹部の者が兵士の逃亡を恐れて火災中、一所に集めて手伝わせなかったからである。
僧侶達は、客殿安置の御開山日興上人のおしたための巨大な御本尊を、どうやら事なく裏の杉林にお移しすることが出来た。そこで初めて安堵の息をはいた。
火勢は、火に火を呼び、盛んである。
僧侶達は、一、二の僧侶を残して、御影様の搬出に駈け戻った。
居残った僧侶の一人が、火の子の飛ぶ空を見上げながら――突然、われにかえったように言い出した。
「御前様は、どうなさったろう?」
「御前様か、さっき玄関のあたりに、たしかおいでになったようだ」
もう一人の僧侶が、事もなげに答えた。
「そうか……えらいことじゃな」
前の僧は、身のすくむ思いであった。
夜毎をこがす火焔、その火焔の反射、火のはぜる無気味な音、僧は、小声で唱題していた。
やがて、御影様も移された。その他の什宝も、ことごとく、次々と杉林に運ばれてきた。
――御本尊様は御無事だぞ。
僧侶一同の胸中に、安堵の歓びが湧いた。火勢は、なかなか衰えを見せない。
空が、かすかに白んできた。
焔の色も、色褪せてきた。
人々の顔も、ぼんやり、互いに見分けがついて来た。――その時、一人の僧侶が、人々の顔をのぞきながら、大きな声で叫んだ。
「御前様は?」
僧侶達は、互いに顔をたしかめあった。そして、驚愕した表情で口々に叫んだ。
「御前様がいない‥…」
「…‥御前様がいないぞ」
「誰か知らないか」
さっき、居残った一人の僧侶が呟くように言った。
「確か、玄関でお見かけしたようだが……」
その声は、いかにも、自信が無さそうに響いた。
僧侶達は、いっせいに駈けだした。いや、ころげるように走り出した。ある僧は、杉林を出て、塔中へ。ある僧は、ふたたび客殿の方へ。ある僧は、裏の杉林の方へ……と。
一団の僧は客殿の周囲をあわただしく駆けまわった。そこにも、猊下の姿はなかった。
誰に聞いても、わからない。
「塔中のどこかの坊に、いらっしゃるに違いない」
「御影堂かも知らぬ」
火勢が衰えるにつれ、不安は、いよいよつのってきた。みな蒼白である。僧侶達は再三、境内のあちこちに散り、集まり、また、散っていった。
塔中の十二坊を、ことごとく探しまわった。御影堂も見た。あちこちの杉林にも、人影はなかった。
時は刻々とすぎ、空は明るくなった。
しかし、猊下のお姿を見た者はなかった。
隈なく、探索した僧侶たちは、自然とまた、客殿の焼け跡に戻って来た。誰の顔も、煤けて、眼ばかり、ギョロリとしていた。
顔を見合わせると、言い知れぬ、不安を互いの顔に読みとった。
火は、消えた。
火事場の異様な、臭気が漂っている。白い煙がくすぶりつづけている。
僧侶たちの目は期せずして二階の管長室にそそがれた。そこを、大奥と呼びならわしていた。
階段は黒こげになっていたが、形はそのまま残っていた。
学童たちは、塔中の宿舎にひきあげていた。朝鮮義勇軍の兵士たちや、警防団の人達は、焼け跡の所々にかたまり、がやがや話し合っていた。
何を思ったか、一人の僧侶が、大奥の焼け跡のなかに入り、階段の方へ進んでいった。
「おい、危いぞ」
「気をつけろ!」
焼け跡の周囲から、鋭い叫びが響いた。人々の眼は、いっせいにその僧侶の背にそそがれた。
その僧侶は、棒切れで、階段を一段一段たたきながら、足元の安全をたしかめ、昇りはじめた。
彼の姿が消えた。
しばらくすると、激越な、悲痛な声が聞こえてきた。
「御前様! 御前様!…」
一瞬、人々は息をのんだ。
その一瞬が過ぎると二、三人の僧侶も、焼け跡に飛び込み、階段へと駈けていった。
焼けただれた管長室には、第六十二世日恭猊下が、おいたわしくも、身を火焔に自ら焼き、端座したままの姿であられたのである。
しかも、正装であり、袈裟をかけた、お姿である。そして、一閻浮提総与の大御本尊を、御安置した、御宝蔵の方に向かっていた。
猊下はお逃げになることは、いくらでも出来たのである。その証拠に、数百人の羅災者のなかで、負傷者ほ一名もなかった。
客殿の、焼亡とともに、何故に、吾が身をみずからお焼きになったのか ――凡庸の推察は、差し控えなければならない。しかし、側近の老僧には、深く思いあたることがあった。
一人の老僧は、前日の、猊下のお言葉を思い出した。
戦況の日に日に、非なることに話が及んだ時、猊下は、独り言でもいわれるように、側近の老僧に語った。
「国が亡びるか、否かの時になった。私もいつ倒れるかわからない」
さらに、その数日前――もう一人の老僧にも、猊下は、異常な御覚悟を語っていた。
「……私に、万一のことがあろうと、御相承のことは、お二人の御隠尊猊下(堀日亨上人・水谷日隆上人)がいらっしゃるから、何も心配はない」
さらに、此れより前――猊下は、お一人で文部省を訪れた。身延との合同問題が、国家権力の強圧の下に、実行に移されるばかりになっていた。
猊下は、単身、当局に向かって「合同、不承知」をば厳然と宣言して帰られたのである。
――日蓮大聖人の、正法正義を継承する本宗は、断じて、邪法邪義たる身延をはじめ、いかなる宗とも絶対に合同はせぬlと。
その毅然たる態度、迫力に、役人は驚いた。なおも猊下は、――たとい今、頸を切られてここに死すとも合同せず――と叫ばれて、ここに正宗の法水を護り抜かれて帰られた。じつに、日蓮大聖人の、幕府権力に対決した時のお姿が、そのまま拝されるのである。
-----------------------------------------